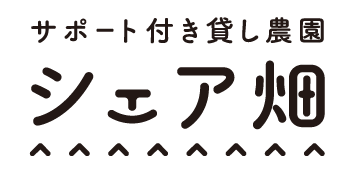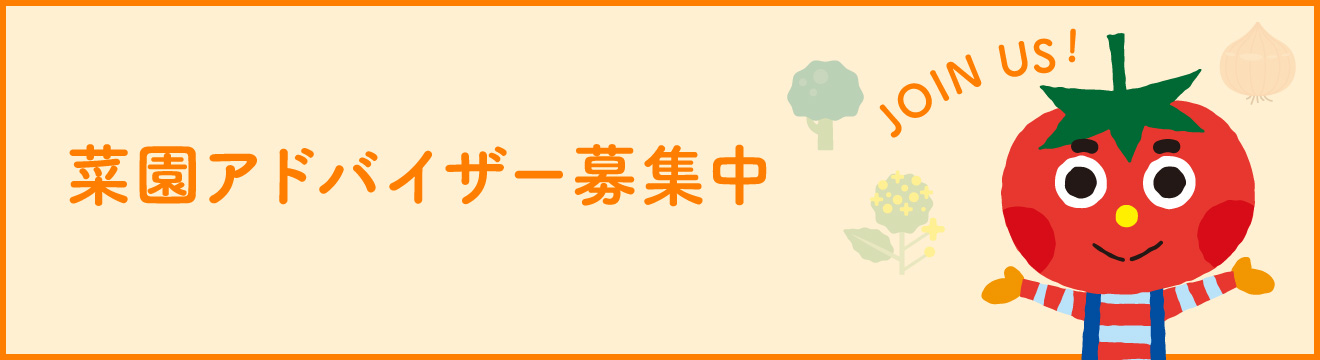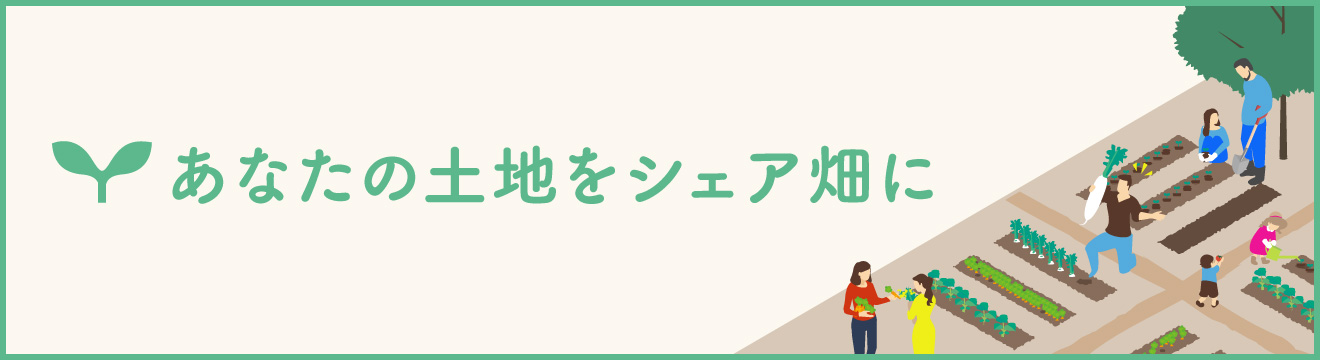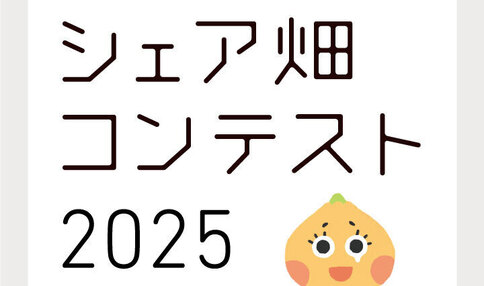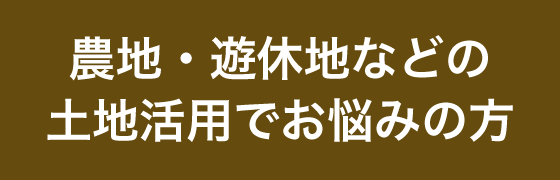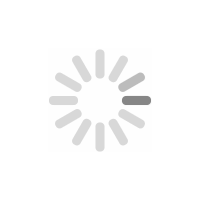ジャガイモを上手に栽培する方法。栽培で起こる疑問トラブルも詳しく解説
|目次
■ジャガイモはどんな野菜?
・ジャガイモの種類
・ジャガイモの生育条件
・ジャガイモの旬の時期
■ジャガイモの栽培の手順
・プランターでのジャガイモの栽培に必要なもの
・種芋を準備する
・土作り
・種芋の植え付け
・ジャガイモの植え付けの時期は?
・芽かきについて
・追肥・土寄せ
・ジャガイモの収穫時期と収穫方法は?
・ジャガイモで気を付けておきたいことは?
■ジャガイモの栽培で連作障害が発生する原因と対策について
・連作障害を起こさない方法は?
■ジャガイモの栽培で気を付けるべき病気について
・イモ(塊茎)に発生する主な病気3選
そうか病
乾腐病
軟腐病
・ジャガイモの茎葉に発生する主な病気3選
モザイク病
べと病
青枯病
・ジャガイモの病気の予防と対策について
病害虫対策
感染した部分を取り除く
風通しと水はけの良い土壌環境の整備
感染した土は処分する
■ジャガイモの栽培で重要な害虫対策について
・アブラムシ
・テントウムシダマシ
・ヨトウムシ類
・予防
■ジャガイモの栽培で悩んだら、菜園アドバイザーに相談してみよう
■まとめ

ジャガイモはどんな野菜?
ジャガイモはトマトやナスと同じナス科の野菜で、南米のアンデス山脈の高地が原産です。
日本での主産地は北海道で、国内の約8割を占めています。
保存がきく野菜として人気があり、ビタミンCやカリウムなどの豊富な栄養を含んでいます。
ジャガイモの種類
ジャガイモは春と秋の年2回植えることができます。
春と秋の栽培方法に大差はありませんが、それぞれの植え付け時期に適した品種があります。
種類も豊富なので、お好きな味や食感で選んでみるのもおすすめです。
<春作>
男爵
ホクホク系品種といえば男爵です。
キタアカリ
男爵より黄色く、粉質でホクホクとした食感があります。
<秋作>
デジマ
煮崩れしにくい秋作向けの品種です。
アンデスレッド
さつまいもに似た赤色で甘みがあります。
ジャガイモの生育条件
比較的涼しく乾燥した気候を好みます。
品種にもよりますが、発芽の適温は18〜20℃で、生育の適温は15〜25℃です。
ジャガイモの旬の時期
全国各地で通年栽培・出荷されていますが、市場に多く出回る時期は春と秋の年2回です。春には九州で秋に植え付けたものが、秋には北海道で春に植え付けられたジャガイモが多く出荷されます。
よく耳にする新じゃがは、鹿児島や長崎から3〜5月に出荷されるものと、北海道産の7月に出荷されるものが有名です。
ジャガイモの栽培の手順
ジャガイモは植え付けてから、およそ100日ほどで収穫できる作物です。
種芋を準備して、土づくりを済ませましょう。
ジャガイモは畑やプランター、どちらでも育てられますが
ここでは、家庭菜園で始めやすいプランターでの栽培方法について解説します。
プランターでのジャガイモの栽培に必要なもの
家庭菜園でプランターでジャガイモを育てる場合、下記の準備が必要です。
・種いも(スーパー等で売っている食用の芋ではなく、ホームセンターや園芸店で販売されている「種いも専用」の芋を購入することをオススメします。)
・有機野菜培養土
・プランター(深さ40cmぐらいの長方形)
・鉢底石
・肥料

種芋を準備する
大きめの種芋は3〜5mmぐらいの太めの緑色の芽が出たら、芽が集まっている部分を通るように種芋を切ります。
一片の重さは、30〜50gが目安です。
種芋を切ったら、風通しの良い場所に数日間置き、切り口を自然乾燥させます。
小さめの種芋の場合は切らなくてもそのまま植え付けができます。

土作り
プランターは、日当たりと風通しの良い場所に置きましょう。
ジャガイモをプランターで栽培する場合、市販の有機野菜培養土を使うのが最も手軽です。
有機野菜培養土は、化学肥料を使用せず土と有機肥料が適切に配合されていてプランター栽培に適しています。
土の水はけをよくするために、鉢底石という軽石を土の下に敷き詰めておきます。
次に、その上から土をプランターの半分の高さまで入れます。
種芋の植え付け
種芋同士の間隔を20cmくらいあけて植え付けます。
浴光育芽を終えたあとに種芋を切り分けた場合は、切り口が下を向くように植えてください。
種芋を置いたらプランターの上部から3cm程度の深さを残して、種芋が隠れるように覆土します。
軽く手で平らにならしたら、たっぷりと水やりをして植え付けは完了です。
ジャガイモの植え付けの時期は?
ジャガイモの植え付け時期は、春と秋の2回です。
関東を基準にした場合、春は3〜4月中旬頃、秋は8〜9月頃に植え付けます。
春の植え付け
ジャガイモは植え付けてから、100日ほどで収穫できる作物です。
3月上旬に植え付けた場合、収穫の目安は6月中旬になります。
注意すべき点として、ジャガイモは収穫時に雨が降っていると傷みやすくなります。
晴れた日に収穫しましょう。
初心者の方には、難易度の低い春の植え付けをおすすめします。
秋の植え付け
寒冷地以外ではジャガイモを秋にも植え付けることができます。
暑さが落ち着く8月下旬から9月上旬に植えた場合、収穫の目安は11〜12月頃です。
春と比べて大きさや収穫量が少なめだったり、暑さで種芋が腐りやすかったりと春に比べると栽培の難易度は少し上がりますが、品種によってはホクホクとした食感のジャガイモを楽しむことができます。
秋作の場合、気温が高く種芋が腐りやすくなります。切り口から病原菌が繁殖しやすいので、種芋はカットせずに植え付けることをオススメします。
芽かきについて

芽かきとは、ジャガイモから複数の芽が出てきた時に、優良なものを選抜して残し、残りの芽を引き抜く作業のことです。
間引きをイメージすると分かりやすいかと思います。
芽かきのタイミングは、1つの種芋から3〜5本の芽が出て、10cm前後まで伸びた時です。芽が気になっても、ある程度の長さがなければ芽かきはやりにくいので注意しましょう。
コツは、種芋が動かないよう土をしっかり押さえて、1本ずつ慎重に引き抜くことです。
芽かきをしないまま生長した場合、実の部分に十分な栄養が行き渡らず、小さなじゃがいもが多くなるので、芽かきはしておいた方が良いでしょう。
追肥・土寄せ
ジャガイモに必要な追肥は2回です。
芽かきをした直後に1回目の追肥を施します。
肥料を与え終わったら、ジャガイモに日光が当たらないよう土を株元に寄せます。
この作業を土寄せと言い、ジャガイモの表面が緑色になるのを防ぐためです。(緑色の部分にはソラニン等の有毒な成分が含まれています)
2回目の追肥は、芽かきから2〜3週間後の蕾がついた時期に、同じ手順で行なってください。

ジャガイモの収穫時期と収穫方法は?
収穫時期の目安は、種芋を植え付けてから約100日後です。
葉や茎が黄色く枯れてきたら、収穫時期を迎えたと考えて良いでしょう。
収穫の下準備として、2〜3日前から水やりをやめて土を乾燥させておきます。
土が乾いたらプランターをひっくり返して、芋がゴロゴロと出てきたら収穫は完了です。
ジャガイモで気を付けておきたいことは?
皮がむきづらいほどの小さいジャガイモには、天然の毒性を持った「ソラニン」という物質の含有率が高いことで知られています。
ジャガイモの芽と皮には、「ソラニン」や「チャコニン」が含まれている場合があるため、これらの部分を十分取り除くことが大切です。
また、皮部分が緑色に変色しているジャガイモにも注意が必要です。
ジャガイモの緑化は、店先や保存していた場所で光に当たりすぎたジャガイモによく見られます。
緑化したジャガイモには、皮付近に通常より多くソラニンとチャコニンを含んでいます。
ジャガイモを保存する場合は、暗所で保存するようにしましょう。

ジャガイモの栽培で連作障害が発生する原因と対策について
ジャガイモは2~3年ぐらいは同じ場所で育てていても大丈夫ですが、
長年にわたって同じ場所で育て続けると、連作障害が出てくる場合があります。
また、ナス科の作物は特に連作障害が出やすいと言われています。
ジャガイモはナス科ですが、同じ「科」の作物を前や後に植えてしまうと連作障害が
起こりやすくなるため、ナスやトマト、ピーマンなどの野菜は続けて同じ土で植えないようにしましょう。
プランターであれば、土を変えたり別の植物を植える等の対応をしましょう。
連作障害を起こさない方法は?
連作障害を起こさないためには、いくつかのやり方があります。
輪作
農作物を一定の順序でローテーションして栽培する方法です。
周期的に作物を変えることで、同じ「科」の連作を回避します。
土の消毒
前の作物に集まっていた病害虫を駆除し、新しい作物のために土壌環境を整える方法です。真夏の太陽熱や真冬の寒さを利用した消毒の方法があります。
時間はかかりますが、自然に近い環境を保てるというメリットがあります。
時間をおく
作物を植えない期間を設けることで、土を回復させる方法です。
数年単位の時間がかかるという欠点があります。
安全な種芋の使用
食用や前シーズンのジャガイモを種芋として使用する場合、その時点でウイルスや細菌に汚染されている場合があります。
なるべく、ホームセンターや園芸店で販売されている種芋を購入するようにしましょう。
ジャガイモの栽培で気を付けるべき病気について
ジャガイモには、地面に埋まっているイモの部分に発生する病気と、茎葉の部分に発生する病気があります。
イモ(塊茎)に発生する主な病気3選
そうか病
ジャガイモの部分にかさぶたのような赤褐色の斑点が発現します。
味に影響はありませんが、見た目が悪いため商品としての出荷はできません。
土壌がアルカリ性に傾くことで発病しやすくなります。
乾腐病
傷がついている部分が陥没し、徐々に拡大していきます。
多湿の状況下では腐敗が進み、ミイラのように乾燥してシワができます。
内部は空洞化し、白色のカビが発生します。
土壌を水はけの良い状態にすることが予防となります。
軟腐病
地面に触れている葉や茎が黒く変色して溶けたように腐敗します。
独特の悪臭を放つので、匂いで発覚することもあるようです。
近くの健康なジャガイモにも広がるので、感染が発覚した場合は、該当するジャガイモを速やかに取り除きましょう。
カビ由来の病気なので、水はけと風通しの良い環境を作ることが予防となります。
ジャガイモの茎葉に発生する主な病気3選
モザイク病
葉に黒い斑点が発現したり、色が抜けてモザイク状になります。
原因となるウイルスをアブラムシが運んできて感染するので、防虫ネットを利用して対策しましょう。
べと病
葉や茎が黄色〜茶色に変色します。
雨や曇りといった多湿の環境が続くと発病しやすくなります。
急激に蔓延し、軟腐病につながる場合もあります。
カビ由来の病気なので、水はけと風通しの良い環境を作ることが予防となります。
青枯病
葉が枯れずに青々としたまま、葉や葉柄が萎れます。
進行が早いため、発病してしまえば治療する時間はありません。
発病した株と周辺の土を丸ごと処分して、健康な株への感染を食い止めることに専念しましょう。
青枯病は土壌から発生し、多湿の環境を好む病気です。
多湿にならない土壌作りが予防となります。
ジャガイモの病気の予防と対策について
病害虫対策
防虫ネットなどを使用し、害虫の侵入を防ぎましょう。
しかし、侵入を完全に防ぐことはできないので、アブラムシなどの病気を媒介する虫は発見次第、駆除しておきましょう。
周辺の雑草を抜いておき、虫の隠れ場所を無くしておくのも良い方法です。
感染した部分を取り除く
斑点や腐敗、変色など、病気に感染している部位または株を発見した場合は、速やかに取り除きます。
取り除いた部位は他の作物に触れさせず、ゴミ袋に入れるなどして処分しましょう。
日頃の観察で見落としがないよう、葉の裏もチェックするようにしてください。
風通しと水はけの良い土壌環境の整備
ジャガイモが病気になる場合、多くはカビが発生原因です。
カビは高温多湿の環境を好むため、水はけと風通しの良い土壌作りを行いましょう。
感染した土は処分する
1度でも病気が発生した土は、次に栽培する作物へ絶対に使い回してはいけません。
次の作物も、再び同じ病気にかかってしまう可能性があります。
病気が発生してしまった土は、必ず処分するようにしましょう。
ジャガイモの栽培で重要な害虫対策について
ジャガイモは比較的、害虫の影響を受けやすい農作物です。
特に対策が必要な虫を把握し、害虫対策に役立ててください。
アブラムシ
アブラムシはウイルスを媒介するため、特に対策が必要な害虫です。
体長は5mm以下と小さいですが、群れで農作物を襲うので、大きな被害を発生させます。
テントウムシダマシ
10月上旬に発生して、葉や実を食害します。
食害された場所から病気に感染する場合もあるので、対策が必要です。
体長は7mm程度で、28個の斑点が特徴です。
ヨトウムシ類
4〜6月と9〜10月に発生して葉を食害する、夜行性の害虫です。
非常に食欲が旺盛なので、葉を食べつくしてしまうこともあります。
予防
侵入の防止
まずは、防虫ネットを設置して害虫の侵入を防ぐことが重要です。
ただし侵入を100%防ぐことはできないので、見つけた場合は潰すなどして駆除しましょう。
土壌環境の整備
害虫は基本的に湿気が多い環境を好みます。
水はけと風通しの良い土壌環境を作り、害虫の発生・増殖を食い止めましょう。
周辺の雑草や枯葉を処分することも、害虫対策には効果的です。
ジャガイモの栽培は初心者でも可能?

ジャガイモの栽培方法についてご紹介しましたが、お役に立てたでしょうか。
ジャガイモは栽培の難易度が低く、初心者でも比較的簡単に育てられる野菜です。
ただし、初めての野菜作りは分からないことが多いと思います。
野菜作りに興味があるけれど、「どう始めればいいかわからない」「管理に自信がない」という方には、「サポート付きの貸し農園サービス」がオススメです。
菜園アドバイザーが常駐しており、初心者でも安心して野菜作りを楽しむことができます。
ぜひこの機会に、新しい趣味としての農業に挑戦してみてはいかがでしょうか?
きっと、新たな楽しさや発見を得ることができるはずです。
ジャガイモの栽培で悩んだら、菜園アドバイザーに相談してみよう
農作業初心者・未経験者の方で、自家栽培や無農薬の野菜を育ててみたいけど、どうしたらよいかわからないという方におすすめしたいのが「シェア畑」です。
シェア畑とは、誰でも「自分だけの畑」が借りられるサービスです。シェア畑では、経験豊富な菜園アドバイザーが的確な栽培サポートを行っており、さまざまな栽培に関する相談が可能です。定期的に実演付きの講習会もあり、その後のフォロー体制も充実しています。
まずは気軽に参加できる 無料オンライン説明会に参加 して、近所のシェア畑への見学をおすすめします。
★無農薬・無化学肥料の野菜作りを体験してみませんか?
手ぶらで通えるシェア畑は菜園アドバイザーのサポート付き。だから初心者でも安心して野菜作りが楽しめます。
近くのシェア畑を見てみる>>