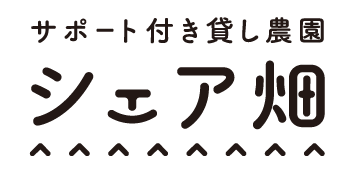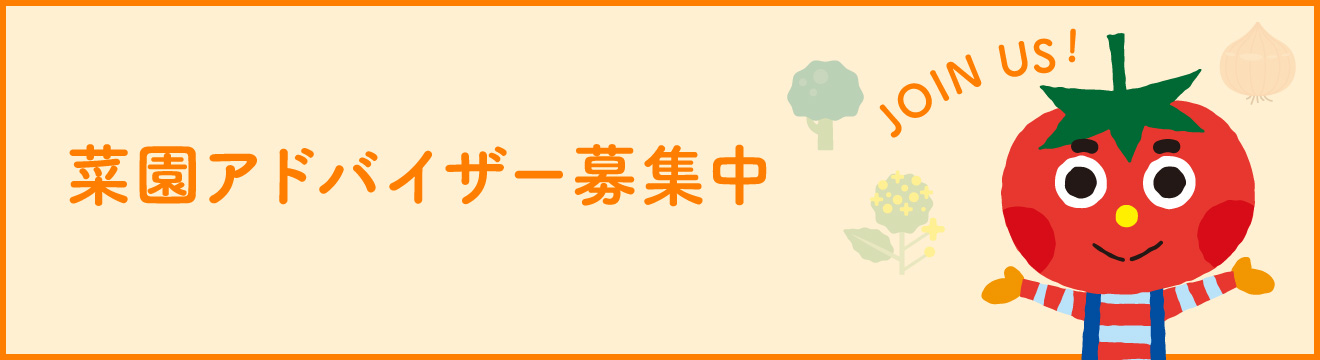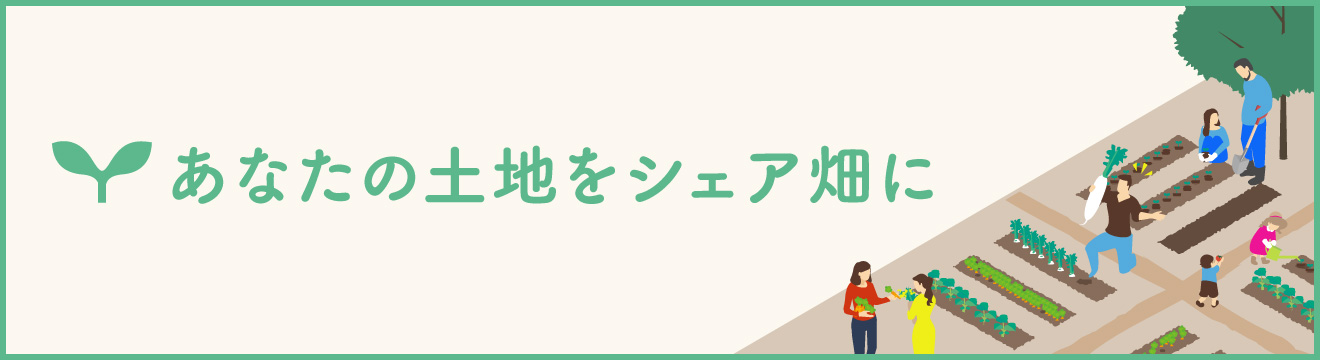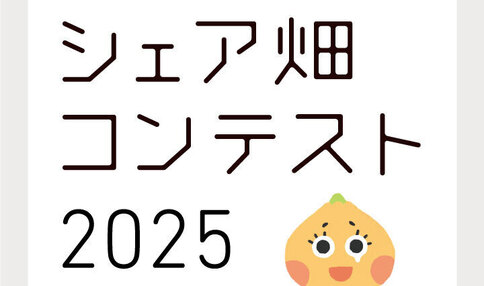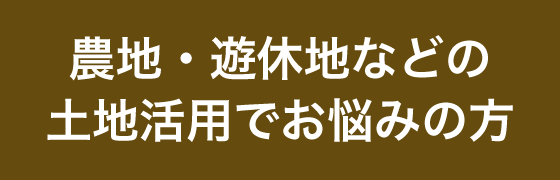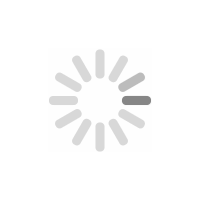|目次
■ビーツはどんな野菜?
■ビーツの生育条件
■ビーツの旬の時期
■ビーツの栽培の手順
■ビーツの栽培で気を付けるべき主な病気について
■ビーツの栽培で重要な害虫対策について
■ビーツの栽培は初心者でも可能?
ビーツはどんな野菜?
ビーツはアカザ科に属する根菜で、その鮮やかな赤紫色が特徴的です。
別名「テーブルビート」や「赤カブ」とも呼ばれ、ヨーロッパや中東では古くから食されてきました。
根の部分だけでなく、葉も食べられるため、捨てる部分が少なく非常に実用的な野菜です。
ビーツは鉄分や葉酸、カリウムを豊富に含み、栄養価が高いことで知られています。
特に貧血予防や血流の改善に効果が期待されており、健康志向の方に人気のあるスーパーフードとして注目されています。
ビーツの生育条件
ビーツを元気に育てるためには、以下の条件を整えることが大切です。
1. 温度
ビーツは冷涼な気候を好みます。生育適温は15〜20℃で、暑さに弱いため、夏場の栽培は避けた方が良いでしょう。
秋や春の涼しい季節に適しています。
2. 日当たり
日当たりの良い場所で育てることで、根の成長が促進されます。
ただし、真夏の直射日光が強い時期には、半日陰での管理が適切です。
3. 土壌
水はけが良く、適度に湿った肥沃な土壌が理想的です。植え付けの前に苦土石灰を混ぜて、土壌pHを6.0〜7.0に調整すると良い結果が得られます。
ビーツの旬の時期
ビーツの旬は、春と秋が中心です。
種まきは3月〜4月または9月〜10月が適期で、種をまいてから60〜90日で収穫が可能です。
栽培期間が比較的短いため、家庭菜園でも気軽に挑戦できるのが魅力です。
ビーツの栽培の手順
ビーツの栽培には以下の手順を踏みます。
1. 種や苗の準備
ビーツは種から育てるのが一般的です。
種は二重殻に包まれているため、種まき前に一晩水に浸しておくと発芽率が上がります。
2. 土作り
栽培場所には、水はけの良い肥沃な土壌を用意します。
植え付けの1〜2週間前に苦土石灰を混ぜ、元肥を施して土を整えます。
3. 種まき
種をまく際は、株間を10〜15cm程度空けて、1cmほどの深さに植えます。
発芽後に間引きを行い、健康な苗を残します。
4. 肥料管理
発芽後から収穫までの間、2〜3週間ごとに追肥を行います。
窒素分が少なめの肥料を選ぶと、根の肥大が促進されます。
5. 水やり
土が乾燥しないよう、適度に水を与えます。ただし、過湿は根腐れの原因となるため注意が必要です。
ビーツの栽培で気を付けるべき主な病気について
ビーツ栽培中に注意すべき病気には以下のようなものがあります。
1. ベト病
葉に水浸状の斑点が現れる病気です。
風通しを良くし、湿度を下げることで予防が可能です。
2. 根腐れ病
過湿や排水不良が原因で発生する病気です。
水はけの良い土壌を用い、適切な水管理を行いましょう。
ビーツの栽培で重要な害虫対策について
ビーツに付きやすい害虫は以下の通りです。
1. アブラムシ
茎や葉に付着し、養分を吸収する害虫です。早期発見と駆除が重要です。
2. ヨトウムシ
夜間に活動し、葉や茎を食害します。防虫ネットの使用や手作業での駆除が効果的です。
ビーツの栽培は初心者でも可能?
ビーツは比較的育てやすく、初心者でも挑戦しやすい野菜です。
短期間で収穫ができるため、家庭菜園にも最適です。プランター栽培も可能で、限られたスペースでも楽しめるのが魅力です。
★「シェア畑」では誰でも気軽に農業と触れることができます
菜園アドバイザーのサポートが付いているので、安心して畑での野菜作りを楽しめます。自然の力を利用した無農薬・無化学肥料の野菜作りを体験してみませんか。
近くのシェア畑を見てみる>>